シンポジウム講演募集テーマ
S1.溶液化学の新しい展開
< New Development of Solution Chemistry >(主催:溶液化学懇談会)
エネルギー、ライフサイエンスをはじめとする現代の基幹技術において、将来の大きなブレークスルーを達成するには、溶液中の分子間相互作用の解明が必要不可欠である。本シンポジウムでは溶液化学全般にわたる新しい意欲的な研究発表を募集する。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒990-8560山形市小白川町1-4-12 山形大学理学部物質生命化学科 亀田恭男(TEL 023-628-4581, FAX 023-628-4591, E-mail:kameda@sci.kj.yamagata-u.ac.jp)
S2.分子機能電極−界面電子移動制御とその応用
< Molecularly Functionalized Electrodes−Fundamentals and Applications >(主催:分子機能電極研究会)
電極−溶液界面の分子レベルでのデザイン・改質の基礎的評価と応用を探る研究発表を募集。有機化合物、無機化合物、金属錯体による単分子修飾、金属ナノ微粒子、コロイド粒子、アドアトム、LB修飾、高分子被膜、薄膜形成などによる界面制御および電極触媒材料、リチウム電池・電子ペーパー用活物質の化学修飾、固体活物質粒子薄膜層の相変化の電気化学、デバイス、センサ等への応用。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒226-8502 横浜市緑区長津田町4259 東京工業大学大学院総合理工学研究科物質電子化学専攻 大坂武男(TEL 045-924-5404, FAX 045-924-5489, E-mail:ohsaka@echem.titech.ac.jp)
S3.光電気化学と光エネルギーの変換・貯蔵
< Photoelectrochemistry, Light Energy Conversion and Storage >(主催:光電気化学研究懇談会)
本シンポジウムでは、光励起状態がかかわる電気化学反応の基礎と応用の分野を対象に、新しい反応の提案、反応の解析、これに基づいたデバイスやシステムの開発技術を討論します。太陽電池、光電変換、光触媒や光浄化、電池化学発光などをテーマとして、エネルギーの変換・貯蔵の効率、さらには低環境負荷の手段など産業界での応用に向けた話題を集めて、活発な討論を交えます。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒225-8502横浜市青葉区鉄町1614 桐蔭横浜大学大学院工学研究科 宮坂 力(TEL 045-974-5055, FAX 045-974-5657, E-mail:miyasaka@cc.toin.ac.jp)
S4.有機電気化学の新展開
< New Development of Organic Electrochemistry > (主催:有機電気化学研究会)
アクリロニトリルの電解還元二量化反応によるアジポニトリル(ナイロンの原料)合成の工業化を契機に、有機電気化学は急速な進歩を遂げ、今日では先端分野としての基盤を確立しつつある。本シンポジウムでは有機電気化学のさらなる飛躍的発展を目指した新しい先端的研究領域の開拓と創造について多角的、総合的に討論し、次世代に繋がる有機電気化学の新しい展開を図る場としたい。新しい原理、概念あるいは方法論に基づく有機電極反応や反応制御法などの研究発表を広く募集。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒226-8502 横浜市緑区長津田町4259 東京工業大学大学院総合理工学研究科 跡部真人(TEL/FAX 045-924-5407, E-mail1:atobe@echem.titech.ac.jp)
S5.生命科学と電気化学
< Life Science and Electrochemistry >(主催:生物工学研究会)
バイオエンジニアリング、バイオメディカルエンジニアリング、ライフサイエンスに関連する電気化学の研究全般。生体関連物質の電極反応、バイオセンサー、バイオセンシング、バイオエレクトロニクス、遺伝子発現制御、細胞・生体膜の機能解析、バイオナノ・マイクロデバイス、細胞操作、バイオイメージング、などに関する技術開発、基礎研究から、医療・医薬・食品・化生品・環境・エネルギーなどの分野への応用研究まで広範囲の研究を募集。招待講演ないし依頼講演および一般講演で企画。
問合先:〒184-8588小金井市中町2-24-16 東京農工大学大学院工学府生命工学専攻 早出広司(TEL/FAX 042-388-7027, E-mail:sode-lab@cc.tuat.ac.jp)
S6.溶融塩化学の将来展望
< Future of Molten Salt Chemistry >(主催:溶融塩委員会)
溶融塩、イオン液体のもついわゆる「高いイオン性」を利用した様々な研究開発の試みが近年活発に行われ、一定の成果を挙げつつある一方で、その課題も浮き彫りとなってきた。本シンポジウムでは、今後の溶融塩化学の展望も込め、幅広い分野、広範な視点からの溶融塩、イオン液体を対象とした研究発表を募集する。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒565-0871吹田市山田丘2-1 大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻田中研究室
平井信充(TEL/FAX 06-6879-7468, E-mail:msc@electrochem.jp)
S7.固体化学の基礎と応用−固体材料の合成・物性・反応性
< Fundamental and Application of Solid Chemistry−Synthesis, Properties, and Reactivity of Solid Materials >(主催:固体化学の新しい指針を探る研究会)
固体化合物および固体材料の合成・物性・化学反応など固体化学の分野には、各種興味ある現象や理論的解釈が含まれる。固体化学全般にわたる意欲的な研究発表を募集。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒152-8552東京都目黒区大岡山2-12-1, s8-16 東京工業大学大学院理工学研究科材料工学専攻 丸山俊夫(TEL 03-5734-3136, FAX 03-5734-3137, E-mail:SolidChem@mtl.titech.ac.jp)
S8.電池の新しい展開
< New Aspects of Battery Technology >(主催:電池技術委員会)
電子機器、電気自動車(EV、HEV、PHEV)、電力貯蔵用等に用いられる一次電池、二次電池の電極材料、電極反応機構、電池構成技術、安全性評価技術等に関する基礎から応用までの広範囲の研究発表を募集。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒563-8577 池田市緑丘1-8-31 産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部門内 電気化学会電池技術委員会事務局 辰巳国昭(TEL 072-751-7932, FAX 072-751-9609, E-mail:denchi@m.aist.go.jp)
S9.燃料電池の展開−材料からシステムまで
< Development of Fuel Cells−from Materials to Systems >(共催:SOFC研究会、燃料電池研究会)
種々のタイプの燃料電池に関連した基礎科学、材料、性能評価、システム、応用技術を含む広い範囲での研究発表を募集。招待講演および一般講演で企画。なお、ポスターセッションも企画(学生および一般、研究会より優秀ポスター賞を表彰、このポスター発表は、シンポジウム名 PFC燃料電池(S9)からお申込み下さい)
問合先:〒158-0082東京都世田谷区等々力8-15-1 東京都市大学総合研究所 横川晴美(TEL/FAX 03-5706-3112, E-mail:h-yokoka@tcu.ac.jp)
S10.キャパシタ技術の新しい展開
< Evolution of New Technologies in Advanced Capacitors >(主催:キャパシタ技術委員会)
モバイル、電子機器用の小形コンデンサから、エネルギー用大容量キャパシタまで、キャパシタ(コンデンサ)の用途は広がりを見せています。これら広範囲にわたるキャパシタの基礎科学、材料技術および利用に関する研究発表を広く募集。周辺領域からの話題提供も歓迎。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒184-8588小金井市中町2-24-16 東京農工大学大学院共生科学技術研究院直井研究室 直井勝彦(TEL 042-388-7174, FAX 042-387-8448, E-mail:capatech@cc.tuat.ac.jp)
S11.工業電解と電解技術のエネルギー・環境技術への展開
< Development of Industrial Electrolysis and Application of Electrolysis for Energy and Environment Technologies >(主催:電解科学技術委員会)
工業電解はソーダ工業、金属精錬、メッキ技術をはじめとする様々な産業を担う技術として着実に進展するとともに、再生可能エネルギーの貯蔵・輸送システムの一翼を担う水電解技術、廃水処理、殺菌、機能水などのエネルギー・環境技術にも展開している。本シンポジウムではこれらの電解に関わる材料技術、システム技術に関する発表を募集。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒240-8501横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5 横浜国立大学大学院工学研究院機能の創生部門 光島重徳(TEL 045-339-4020, FAX 045-339-4024, E-mail:denkai@electrochem.jp, Web-site:http://denkai.electrochem.jp/)
S12.腐食科学と表面制御
< Corrosion Science and Surface Modification> (主催:腐食専門委員会)
金属腐食の解明とその制御ならびに表面改質技術を支える新しい展開に関してシンポジウムを行う。さらに、新規な水溶液プロセスを応用して作成した金属・金属酸化物等の新規表面の機能・物性・構造についても議論する。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒565-0871吹田市山田丘2-1 大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻 藤本慎司(TEL 06-6879-7469, FAX 06-6879-7471, E-mail:fujimoto@mat.eng.osaka-u.ac.jp)
S13.化学センサの新展開
< The Latest Development in Chemical Sensors >(主催:化学センサ研究会)
化学センサは、環境計測、車載および製造工程のプロセス制御、医療診断、アメニティなど種々の分野での最先端センシングデバイスとして実用されている。また、更なる高性能化を目指して、これらセンサのインテリジェント化、マイクロ化が進みつつある。本シンポジウムでは、ガスセンサ、バイオセンサ、イオンセンサ、μTASなどの化学センサ全般について、基礎から応用までの幅広い研究発表を募集。なお、このシンポジウムは第51回化学センサ研究発表会として開催する。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒816-8580春日市春日公園6-1 九州大学産学連携センター三浦研究室内 化学センサ研究会事務局(TEL 092-583-8852, FAX 092-583-8976, E-mail: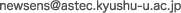 ) )
http://chemsens.electrochem.jp
S14.機能性セラミックスの基礎と応用
< Fundamentals and Applications of Functional Ceramics >(主催:機能性セラミックス研究会)
機能性セラミックスの作製からその特性および応用まで、最近の展開についての研究発表を募集。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒305-0044つくば市並木1-1 物質・材料研究機構光材料センター 島村清史(TEL 029-860-4692, FAX 029-851-6159, E-mail:shimamura.kiyoshi@nims.go.jp)
S15.マイクロ〜ナノ構造形成のための先端技術−エレクトロニクス〜バイオの広範囲な応用展開
< Frontier Technology for Micro- and Nano-fabrication and Materials−Novel Applications from Electronics to Biotechnology >(共催:情報機能材料研究会、電子材料委員会)
微細構造形成はマイクロメートルからナノメートルレベルへ急速に展開し、それに伴い従来の薄膜やリソグラフィ技術に加え、ナノ粒子形成や自己組織化といった新しい技術展開が進んでいる。またその応用範囲も従来のエレクトロニクスからバイオチップのようなバイオテクノロジーまで広範囲にわたっており、今後さらに拡大していくと予想される。本シンポジウムではマイクロメートルからナノメートルまでの微細構造を形成、応用する技術を中心テーマとして扱う。ファブリケーションに関しては薄膜、微粒子作製から微細構造形成技術まで、それに加えそれら微細構造の新しい応用技術について討論する場としたい。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒226-8502横浜市緑区長津田町4259-J2-40 東京工業大学大学院総合理工学研究科物質科学創造専攻 北本仁孝(TEL 045-924-5424, FAX 045-924-5433, E-mail:kitamoto.y.aa@m.titech.ac.jp)
S16.蛍光体とその応用
< Phosphors Materials and Their Application >(主催:蛍光体研究懇談会)
照明、ディスプレイ、医療、センサ、記録、太陽電池などの分野で重要性を増す蛍光体に関する研究発表を募集。蛍光体に加えて、塗布などのプロセス技術、蛍光体を用いたデバイスやシステムも含めた幅広い分野からの発表を歓迎する。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒571-8504門真市松生町1-15 パナソニック(株) AVCネットワーク社技術統括センターAVCデバイス開発センターデバイス第二開発グループ 大塩祥三(TEL 06-6906-3325, FAX 06-6906-1974, E-mail:oshio.shozo@jp.panasonic.com)
S17.クロモジェニック材料の新たな実用化研究
< New Research for Practical use of Chromogenic Materials >(主催:クロモジェニック研究会)
エレクトロクロミズムを中心に行われてきたクロモジェニック材料研究も、近年はサーモクロミック、フォトクロミック、ガスクロミック等への広がりをみせ、新しい機能材料への応用を目指した研究も行われるようになってきた。本シンポジウムでは、このような様々な種類のクロモジェニック材料に関する研究発表を募集。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒463-8560名古屋市守山区下志段味穴ケ洞2266-98 産業技術総合研究所 吉村和記(TEL 052-736-7305, FAX 052-736-7315, E-mail:k.yoshimura@aist.go.jp)
S18.ナノスケール界面・表面の構造とダイナミクス
< Structure and Dynamics on Nano-scale Interface and Surface >(主催:ナノ界面・表面研究懇談会)
表面における反応プロセスならびに界面構造を、ナノスケールで理解することは、基礎・応用の両面において重要である。界面・表面構造、表面分光、反応機構、電極触媒、ナノ微粒子、結晶成長・薄膜形成、センサーなど、広範囲の研究発表を募集。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒263-8522千葉市稲毛区弥生町1-33 千葉大学大学院工学研究科共生応用化学専攻 星 永宏(TEL/FAX 043-290-3384, E-mail:hoshi@faculty.chiba-u.jp)
S19.明日をひらく技術・教育シンポジウム
< Symposium of Technology and Education for the Future >(主催:技術・教育研究懇談会)
明日をひらく技術・教育シンポジウムを開催して、学術的に新規性・独創性のあるもの、工学的技術に関する新規性・独創性のあるもの、教育的な意義のあるものを含む研究成果を発表する学術的交流の場を提供し、さらに、それらの成果を「技術・教育研究論文誌」に査読つきで公開する。審査終了後、随時電子出版(http://bigjohn.fukui-nct.ac.jp/journal/)し、年に1巻で、各巻で2号を印刷し冊子体として発行。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒916-8507鯖江市下司町16-1 福井工業高等専門学校内 技術・教育研究懇談会 吉村忠与志(TEL/FAX 0778-62-8292, E-mail:tadayosi@fukui-nct.ac.jp)
S20.電力貯蔵技術の新しい展開
< New Development of Storage Technology for Electric Energy >(主催:エネルギー会議)
風力、太陽光などの自然エネルギーの電力系統への円滑な連係のためや電気自動車などの移動体用の新しい蓄電池、電力貯蔵技術の開発が進められている。ここでは、これらの蓄電池、電力貯蔵技術に関する基礎から応用までの研究発表を募集。招待講演および一般講演で企画。
問合先:〒305-8568つくば市梅園1-1-1つくば中央第2事業所 産業技術総合研究所エネルギー技術研究部門燃料電池システムグループ 根岸 明(TEL 029-861-5803, FAX 029-861-5805, E-mail:a.negishi@aist.go.jp)
PS.学生ポスターセッション
学生のポスターセッションは約50件を予定(優秀発表には表彰有り)。申込件数多数の場合には一研究室1〜2件とさせていただきます。また、ポスターセッションから一般講演の変更をお願いすることがあります。
PFC.燃料電池(S9)ポスターセッション
学生および一般の方のS9“燃料電池の新しい展開”に関するポスター発表は、このシンポジウム名からお申し込み下さい。燃料電池研究会およびSOFC研究会より優秀ポスター賞を表彰。
問合先:〒158-0082東京都世田谷区等々力8-15-1 東京都市大学総合研究所 横川晴美(TEL/FAX 03-5706-3112, E-mail:h-yokoka@tcu.ac.jp)
◎上記シンポジウムに該当しない場合は下記の一般学術講演分類によりお申込願います。
◎ 一般学術講演分類
1.電気化学反応・基礎一般、応用一般、測定法
2.環境化学
3.半導体材料・電子デバイス
4.その他
|